いわゆるノートアプリって使ってらっしゃいますか? 昔からあるものでいうと、Evernote とかが有名かな?と思います。ノートアプリが出たての頃って「自分用のメモを残しておくツール」「自分用の情報管理ツール」という印象だったのですが、その後、どんどん進化して、今ではチーム用の情報共有ツールとしての側面の方が強いと感じます。Notion とか、One Note とか…色んなツールがあるなーと感じています。そんなノートアプリの世界も、生成AIの登場によって大きく変わろうとしています。今回は Google Gemini が搭載されているノートアプリ NotebookLM について簡単に紹介します。
NotebookLMって、そもそも何?
生成AI以前のノートアプリを使っていて、以下のような気持ちになった人…きっと私だけではないと思います。
- 「後で読みたい」と思って情報を蓄積してきて、もちろん読みたい気持ちはあるけれど…時間がない。
- 「アレもコレも読みたい」と情報を貯めた結果、資料が多すぎて、どれが何だったか思い出せない。
- 「コレ、重要だ!」と思って自分がとったメモなのに…今では何のメモなのか?意味不明になってしまった。
結局のところ、ノートアプリって「上手く情報を引き出せるように日頃から整理しておく」「いざ情報を利用したい際は検索等して情報を見つけてくる」という事をやらないと、蓄積した情報のチカラを引き出せないものでした。
しかし、生成AIが出現する事で「情報の整理」「情報の検索」などという面倒な仕事は AI に丸投げしてしまおう…というコンセプトのノートアプリが生まれました。その1つが今回のテーマであるNotebookLMです。
NotebookLMは、Googleが開発したAI内蔵型のノート作成ツールです。Googleの生成AIである Gemini が搭載されています。基本的な使い方は以下の通りです。
- NotebookLM にアクセスし、ノートを新規作成する。(既存ノートアプリと同様)
- 自分の持っているPDF、Google ドキュメント、テキストなどをアップロードする。(既存ノートアプリと同様)
- Geminiに要約や質問を依頼する。(ここが異なる!)
NotebookLMの特徴は、単なるメモ帳ではなく「自分が読み込ませた情報を元に、AIが内容を理解し、対話できる」という点にあります。この特徴ゆえに、今までのノートアプリとはちょっと違った情報との付き合い方ができます。
実際に使ってみる。
実際に使ってみましょう。まずは NotebookLM にアクセスしてください。Google Workspace を使っている方ならば、NotebookLM Plus が使えるようになっています(Plus とそうでないものの違いは別の機会に記載する事とします)。
まずは「新規作成」ボタンをおして、新しいノートを作りましょう。ノートを作成すると、ソース(=PDFファイル、wordファイル、その他、情報が書いてあるファイル)のアップロードを求められるので、アップしましょう。今回は試しに以下のサイトから情報を取得しました。(政府の大きな方針、リカレント教育、リスキリング、大学における博士育成…など、教育に関して政府から発表されている文章を拾ってきました。実際、これらの文章って長いので、全てをしっかり読むのって大変なんですよね。)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/ap2024.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240326-mxt_kiban03-000034860_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/240510-mxt_syogai03-100000261_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240826-mxt_syogai03-100000976_2.pdf
https://www.gyoukaku.go.jp/review/aki/R06/img/9_2_1_keizai.pdf
「ソース」って場所からすべての PDF をアップロードできます。コレが終わったら、画面中央のチャットって場所に問い合わせを投げ込むことができます。例えば…
日本における博士人材育成の意義と現状、今後について教えてください。
…のような事を投げ込むと、以下のように返してくれます。(相当な長文が返ってくるので、ここでは冒頭部分だけ転載します。)
日本における博士人材の育成について、ソースに基づきその意義、現状、および今後の取り組みについてご説明します。
日本における博士人材育成の意義
博士人材が社会の様々な分野で活躍することは、社会の発展にとって極めて重要であると考えられています ① 。博士人材の持つ高度な専門性や幅広い能力を多様な場で発揮できるようになることが期待されています ① 。文部科学省は、産業界と連携し、博士人材の産業界での活躍を促進することが、我が国の経済・社会の持続的発展を叶えるために重要であるとしています ③ 。また、研究により得られる真理を深く探究する経験や、新たな価値を世界に問う経験は、将来様々なフィールドで活躍するための大きな力となると、学生に伝えられています ①。
これの凄いところは「アップロードした文章・資料を要約してくれる」点、そして(それがテキトーなデマではよろしくないわけですが)「要約文の内容は、実際にアップロードした文章・資料のどこに書いてあるかをリンクしてくれる」点になります。この点は今までのノートアプリには無かった機能になります。
今までのノートアプリとの違い
冒頭の通りですが、「ノートアプリ」と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、Evernote や One Note かもしれません。今までのノートアプリとNotebookLMの違いを表にまとめてみました。
| 比較項目 | 今までのノートアプリ | NotebookLM |
|---|---|---|
| 用途 | メモ・スクラップブック | 資料の理解・活用 |
| 検索性 | キーワード検索 | 意味理解に基づく質問応答 |
| サポート機能 | タグ・フォルダ | Geminiによる要約・FAQ生成 |
| ユーザー負担 | 情報整理が手作業中心 | 情報整理をAIが補助 |
NotebookLMは、自分の書いたメモや集めた資料を単に保存するだけでなく、情報の整理・効率的な情報の引き出しをサポートしてくれるというわけです。これは、従来のノートアプリにはなかった体験でした(もっとも、従来のノートアプリも生成AIのチカラを借りて、どんどん進化していっています)。
NotebookLM の便利なところをまとめてみる
① ソースを明示してくれる
Geminiは、アップロードした資料の中から答えを探すため、「何を根拠にして答えているか」が明確です。これは、安心して活用できる大きなポイントです。単に Gemini に聞くだけだと、デマを伝えてくる(ハルシネーション)可能性があるわけですが、根拠となる文章の引用を付けてくれる事は、その情報を信頼していいのか?そうでないのか?を判断するためにとても重要です。
② 情報を追加できる
Notebookは後から資料をどんどん追加可能です。あるテーマについて深堀りするほど、Geminiがその領域に詳しくなっていきます。1つのテーマについて調べる…なんて場合、見つけた情報を逐次的に追加できるのは、とても便利です。このあたりは元来のノートアプリの良いところを残していると感じます。
まとめ:NotebookLMは「自分の知識資産を活かすためのAI」
NotebookLMは、情報を「記録する」ツールに留まらず、「整理する」「引き出す」という点で、人間の労力を大きく下げてくれるツールだと感じました(もちろん、その情報をどのように理解し、利用するか…は人間に委ねられているわけですが)。今まで情報を貯めておいても「あの話どこだったっけ?」「この資料何だっけ?」と感じる事が多かった私のような人間には、お薦めのツールだと感じました。
今回は紹介だけに留まってしまいましたが(Docs とか mail とかと比べると、人によってはちょっとだけ身近じゃないツールなので…)、今後は活用ケースについて考えていきたいと思います。
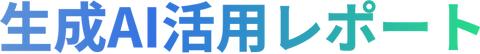
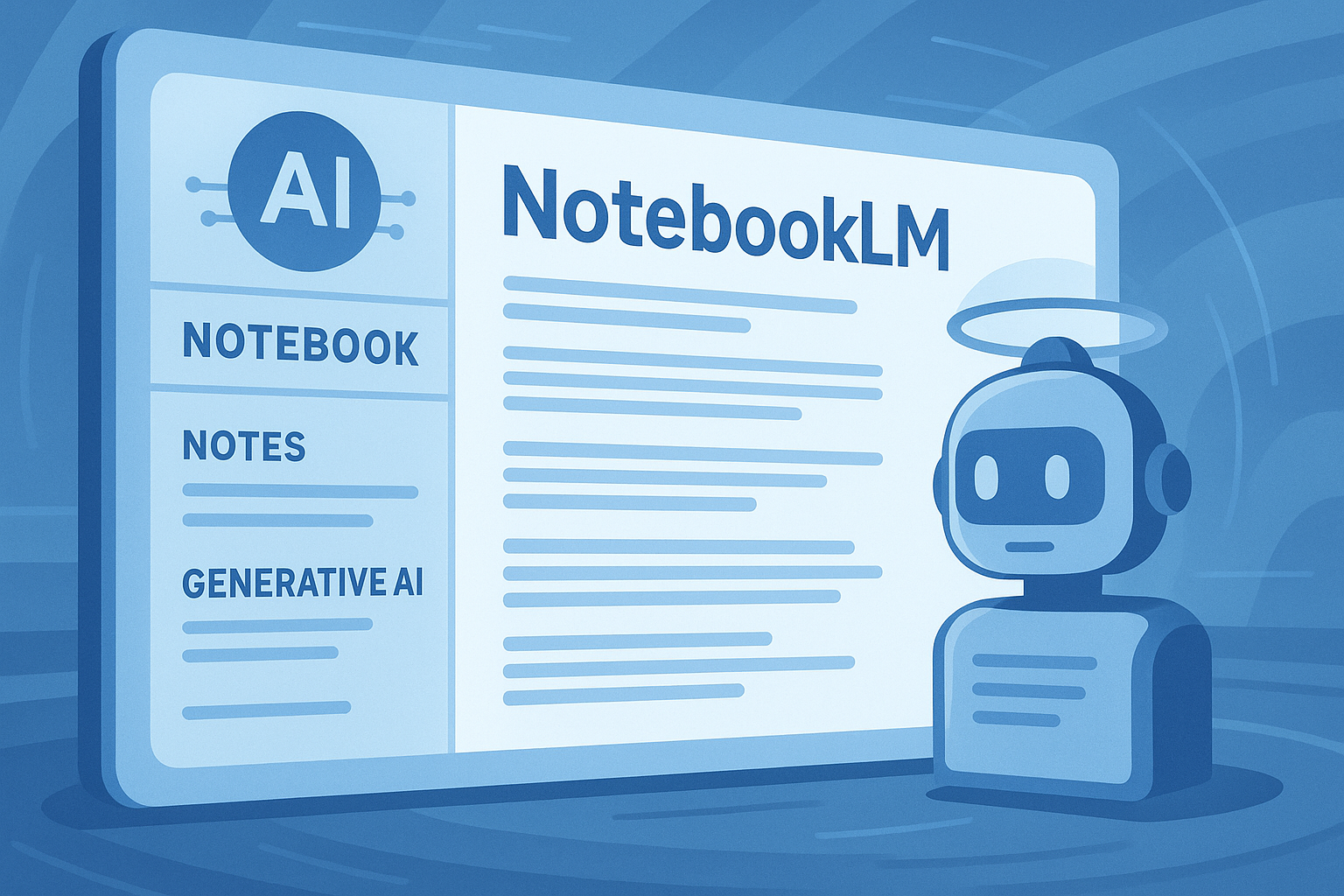


コメント